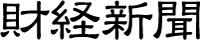関連記事
走行距離課税の行方は? 自動車関連団体、新税や増税に反対の姿勢鮮明
日本自動車会議所の税制部会で、自動車関連団体が24年度税制改正要望案を示し、狙いなどをそれぞれ説明した。今後は各団体で要望案の正式決定に向けた手続きに入る。今回の要望案では、「走行距離課税」など、ガソリン税などの燃料税収が減少することに対する新税や増税には、反対姿勢が鮮明となった。
燃料費高騰はドライバーたちを大きく悩ませているが、忘れてはならないのが導入の話が出ている走行距離課税の存在だ。経済産業省では8月、2024年の税制改正に関する要望書を提出しており、そこには自動車関係諸税の在り方についても記載されている。
経産省の要望書では、車を保有から利用へ移行するという考えが、どうやら主流だ。そのため新しい税金を導入しても、一般市民には影響が少ないと考えているようだ。
加えて地域公共交通へのニーズの高まりもあると考えているが、実際地域交通へのニーズの高まりは、都市部に限られるだろう。つまり地方は、公共交通より自家用車への依存度が根強い。
さらにコロナ禍の影響で、自家用車や自家用バイクでの通勤者が増えた経緯もあり、必ずしも公共交通へのニーズが高まっているとは言い難い。
経産省は、2050年のカーボンニュートラルに向けた動きを加速させようとしている。政府として声高らかにカーボンニュートラルに舵を切っているため、2035年までに新車ではガソリンエンジン車が買えなくなる。
カーボンニュートラルに向けての動きでは、ガソリン税は今後税収が減るため、走行距離課税により、ガソリンを使用しない電気自動車にも課税をしたいのだ。
現在の燃料費高騰は、これからのカーボンニュートラルに向けた取り組みには絶好の機会ととらえている節も大きい。もしここでトリガー条項を発動して税金を安くすれば、電気自動車への移行を考える人を踏みとどまらせる恐れもあるのだろう。
政府としては、カーボンニュートラルの実現を目指しており、それには税金の公平性も必要と考えている。走行距離課税は、車を多く使う地方在住者の負担が大きくなるなど、まだまだ課題も多く、実際に導入されるかは不明瞭だ。
一方で自動車関連団体は、新制度反対案を出すだけでなく、これから来るEV車時代に向けては、公平な税金制度案も出す必要も出てくるだろう。(記事:小泉嘉史・記事一覧を見る)
スポンサードリンク