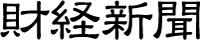関連記事
運転支援装置は大丈夫なのか? ボーイング737MAXの事故はソフトのバグ?
自動車の自動操縦装置(運転支援システムなどを含む)で最も恐ろしい懸念材料が、制御装置のバグ(プログラムの誤り)だ。この疑いがある航空機事故は、かつてからいくつか散見されている。自動車の運転支援システムが普及し始めている時、「制御プログラムの誤り(バグ)」による事故に対する関心がなさすぎる。
【こちらも】米国家道路交通安全局の「自動運転で事故発生率が減少」との発表に対し異議
3月10日、アフリカ東部エチオピアで、乗員・乗客157人を乗せたエチオピア航空のボーイング737MAX8が墜落した。昨年10月にも、インドネシア沖に墜落したライオン航空機(同型機)事故では189人の犠牲者を出した。この2つの事故は類似性が高いと、エチオピア政府は発表した。
事故調査は進められている最中で断言することはできないが、フライトレコーダーやボイスレコーダーの入った「ブラックボックス」は回収されており、今後事故調査は進むものと見られる。両機とも離陸直後に墜落しており、その前に異常な上昇降下を繰り返している。
昨年10月29日に発生したインドネシアのライオン航空610便の事故について調査官は、ボーイング737MAXに新たに搭載された「失速防止システム」に問題があると特定したとしている。飛行機は上昇するに足るエンジン推力がないほど、機首を上げると失速、つまり浮力を失い飛べなくなって墜落してしまう。失速防止システムは、対気速度にふさわしくないほど機首が上がり過ぎて失速しないようにするためのもので、本来はパイロットのミスを防ぐものだ。自動車の運転支援システムのような働きをする。
1994年4月26日、名古屋空港に着陸しようとしていた中華航空140便(エアバスA300-600R)が、コントロール不能となって墜落した時も、「自動操縦システムと手動操作が混在」している時の優先順位問題が指摘された。この時は、パイロットが機首下げの操作をしているのに、自動装置は機首を必要以上に上げてしまい、失速した。
今回のボーイング737MAXの事故では、パイロットは引き上げようとしていたようだが、失速防止装置は機首を下げてしまい、相反する操作となり墜落したようだ。よって自動車の運転支援装置にも、同じようなプログラムミスがないとは言い切れない。事故を防ぐ目的が強い自動運転装置だが、新しいプログラムミスによる事故に対応しなければなるまい。
例えば、「緊急ブレーキが必要もないのに働いて、追突される」などの事故が起きる可能性が考えられる。また正しくブレーキを踏んでいるのに、アクセルが開いてしまうなど、自動運転が進めば進むほどこれらの可能性は大きくなるだろう。さらに飛行機と違って自動車の事故の場合は、詳細に調査が行われることは少なく、現在でも「前方不注意」「ブレーキとアクセルペタルの踏み間違い」などで処理されている可能性はある。日本の製造者責任法、いわゆるPL法も「メーカー側が機械の欠陥でない」と証明できなければ、「欠陥」として欧米並みに処理されるようにしなければならない。これは緊急の課題だ。(記事:kenzoogata・記事一覧を見る)
スポンサードリンク