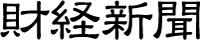関連記事
【知らぬが仏(4)】日本の安全神話は「作業員の腕前」 軽量化新幹線台車亀裂の現実
■金融専門家では経営者は務まらない
最近アメリカ式経営が最先端と信じて疑わない、「金融専門家の経営者」がまことに増えた。投資家たちはそれが最先端と信じて疑わない。それは、当然に「危険が増す」ことは否めない。シミュレーションソフトが進歩して、設計段階であらゆることが判明すると信じてしまっている専門家のコメントも多い。しかし、「ゲームソフト」とは違って、実際に動く「物体」を作るのだ。その間にどれほどの工程を有するのか、考えても分からないシステムエンジンニアがほとんどだ。
【前回は】【知らぬが仏(3)】日本の安全神話は「作業員の腕前」 軽量化新幹線台車亀裂の現実
例えば、「材料取り」をするとき、圧延成形された鉄板の向きに「鉄板にも筋」(鉄板の目)が出来る。材木の木目と同じように、多くの配慮が必要となる。だから、同じように曲げたものでも溶接すると、歪にばらつきが出る。それを読み切るのは至難の業なのだ。それでも作業者は、溶接を部分的に区切って、歪の出ない順番に溶接することを考えなければならない。さらに、今回の亀裂の直接の切欠となったとされる溶接欠陥を出さないように、溶接時の姿勢を考える必要がある。それには3次元に動く「回転冶具」が必要で、溶接部位をできる限り「水平」に置かねばならない。生産技術面からの支援が出来ないと、「軽量化」のため複雑化している部品の溶接は、コストが合わない恐れが出てくる。
それらを十分にするチームを組んで行っていくには、電車の車両では量産数が少なすぎる。おそらくは、川崎重工でも下請けの「作業者の腕前」に頼ってきているだろう。いわゆる「匠の技」だが、情報が不十分な工程であると、間違いも多くなる。「0.5mmしか板厚を削ってはならない」とするマニュアル「作業指導票」を掲示されていながら作業者が無視していたことを考えると、「匠」が状況を把握できていたとは考えにくい。これらの行き違い、勘違い。モチベーションの低下を防ぐために、QCサークルや、ボトムアップシステムなどが存在するのだ。
■【知らぬが仏】「どこで切っても金太郎飴」を実践せよ!
今回は、本当に運が良かった。もう少し新幹線を停車させるのが遅かったら大惨事だった。それほど危険な状態を認識したからこそ「重大インシデント」と判断した理由であろう。JRにも川崎重工にも原因があるのだが、残念ながら「世の中こんなもの!」と言わざるを得ない現実がある。川崎重工と言えども下請けを使っての作業であり、その下請けの現場の管理方法まで統治できているとは到底思われない。多くの作業現場では、作業担当者のモラルと腕前で品質を保持していることが多いのだ。
重大事故になる確率は低く、東日本大震災を予測しなかった原発と同じように、これでは国民の安全は「運しだい」と言える現状で、【知らぬが仏】なのだ。
日本の工業製品の「高度な信頼性」は、「現場作業者の高いモラルと腕前」で支えられてきているのだ。しかし最近は、経営者が「金融・投資の知識」だけで、自社のビジネスモデルの基礎である「品質保証」が成り立つと考え、「現場作業は下々のこと」と受け止めているのが現実だ。「品質の高い日本」が、「利益・投資効率優先」で徐々に浸食されていることに気づくべきだ。
「どこで切っても金太郎飴」を実践できているのであろうか?言い出しっぺのトヨタでさえ、疑ってみることだ。販売店のセールスマン、整備士まで「ガバナンスが徹底しているのか?」考えてみることだ。一部のディーラー経営者の発言を見るだけで、問題を見つけることが出来るのが実態だ。根本的間違いがある。それは、原発事故のように「自然の必要悪」とでもいうべきものなのか?(記事:kenzoogata・記事一覧を見る)
スポンサードリンク