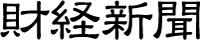関連記事
新アルゴリズムで地球に衝突する可能性ある天体を発見 ワシントン大

地球に最接近する2022 SF289(緑色)の軌道(青色の軌道)を示す画像。金星の軌道はオレンジ色、火星の軌道は赤色。(画像: ワシントン大学の発表資料より)[写真拡大]
太陽系には、誕生して間もない頃から実に数千万個に及ぶ岩石が浮遊している。その大きさは様々で数cm程度のものから、10kmを超える大きなものまである。
かつて恐竜を絶滅に追いやったチクシュルーブ小惑星は10kmを超え、再びこれと同規模の天体が地球を襲えば、人類は瞬く間に滅亡の危機に瀕する。このような危機に備えて、人類は地球近傍天体 (NEO) の中でも地球から約750万km以内にある天体を「潜在的に危険な小惑星」(PHA)として特定し、体系的に探索、その動きを監視している。
PHAは現在2,350個が発見されているが、未発見のものがまだ3,000個以上あると考えられており、小惑星衝突危機の回避にはPHAをくまなく効率よく発見できるシステムの開発が望まれてきた。
このような状況の中、ワシントン大学は、2025年に稼働するチリのベラC.ルービン天文台で採用予定の新小惑星発見アルゴリズム「HelioLinc3D」を開発し、これを用いたテストにより、小惑星2022SF289の発見に成功したと発表した。
同様の既存システムとして、NASAの資金提供を受けハワイ大学が運用している小惑星地球衝突最終警報システム「ATLAS」があり、2015年から運用が開始されている。現在認識されている2,350個のPHAは、ATLASにより発見されたものだ。
ATLASは、口径50cmの2台の望遠鏡で1晩に4回、観測可能な空全体の4分の1を観測し、晴れた日の2晩分のデータを比較することで、新小惑星の発見をするロボットシステムだ。
これに対し、ルービン天文台では、口径8.4mの巨大望遠鏡と3,200メガピクセルカメラで1晩に2回空をスキャンするため、巨大データを従来にない高速で処理できるアルゴリズムの開発が求められていた。
HelioLinc3Dがルービン天文台で本格運用されるのはまだ先の話だが、ATLASをはるかに超える解像度(望遠鏡の集光力は約282倍)で、より多くの新小惑星が自動で発見可能になる。人類はこれを駆使して今後とも地球を襲うPHAをいち早く発見し、それに対して万全の備えをし、滅亡の危機を回避していかなければならない。(記事:cedar3・記事一覧を見る)
スポンサードリンク