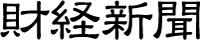関連記事
ふるさと納税の活用でお得に節税を まずは控除上限額の確認から
総務省の発表した最新データによると、2020年度課税におけるのふるさと納税の利用者は約406万人。前年度比約1.03倍としている。同データでは、2009年度課税から2020年度課税までの推移を確認することができるが、年々利用者数が上昇し続けていることが分かる。なお、2009年度課税の利用者数は約3.3万人。
【こちらも】超低金利時代、普通預金口座をどう使う
ふるさと納税は、2008年からスタートした。人口減少による地方税の減収等の対策として、少しでも地方と都心部の税収の格差を無くす目的で運用開始となった背景がある。つまり、自分で選んだ地方自治体に対し、応援する気持ちで寄付ができる。例えば、生まれ育った故郷を離れ都心部で暮らす社会人が、郷里の自治体にふるさと納税として寄付ができるのだ。
ふるさと納税は、正確に言うと寄付金控除の一種である。選んだ自治体に納税をするイメージから「ふるさと納税」と呼ばれるが、実際は自治体に寄付をすることで納税とみなしている。寄付金控除は、認められた団体などに寄付をすることで、控除が発生する。ふるさと納税では、この寄付金控除の仕組みと、さらに返礼品としてさまざまな工夫が凝らされている。
ふるさと納税は、寄付金に関して税金の還付や控除を受けられる。手続きをきちんと済ませると、実質的な自己負担額は2,000円で済む。返礼品がもらえることを考慮すると、消費者にとってはメリットしかないと言える。
対象期間は、1月1日から12月31日まで。つまり11月に入った今の段階で、まだふるさと納税をしていない人でも十分に間に合うのでチャレンジしてみてはいかがだろうか。
まず、実質の自己負担額が2,000円で済む控除額について、シミュレーションをしてみよう。各ふるさと納税サイトでは、シミュレーションツールを提供しており、年収や家族構成、その他の控除など、簡単な項目に答えるだけで控除の上限額を計算できる。
そこで出された控除上限額の範囲内でふるさと納税を行えば、2,000円の自己負担だけで税金の控除や還付が受けられる。さらに返礼品として品物が届いたり、旅行や食事などの体験の機会を得ることができる。
ふるさと納税を行った場合、通常は確定申告により寄付金控除を申請する必要がある、しかし、会社員や公務員などの給与所得者の場合、寄付した自治体が5団体以下であれば「ワンストップ特例」という制度を使うことで、確定申告をしなくてよい。ただし、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、ふるさと納税以外でも確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例が使えないので注意が必要である。
ふるさと納税という制度自体は、得する制度であることは何となく知っている人が多いだろう。しかし、手続きや仕組みが煩雑なイメージから、まだ浸透していない感じも否めない。最近はオンラインで簡単に完結する場合がほとんどであることから、まだ行ったことがないという人は、各種ふるさと納税サイトで情報収集を進めてみてはいかがだろうか。(記事:大野 翠・記事一覧を見る)
スポンサードリンク