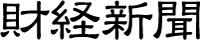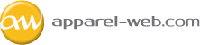関連記事
【インタビュー】「2018年。3年後のWeb戦略」モノ、ブランド、ヒト。すべてに“きめ細かく” マッシュスタイルラボ好調の秘密【後半】
■ファミリーだから、競わず助け合う
―素晴らしい関係ですね。今こうしてお話を聞くだけでも、店舗責任者である鈴木さんとオンラインストア責任者である塩澤さんの2人の仲が良く、しっかりコミュニケーションしていることが伝わってきます。
 清水真紀氏(以下、清水):私は2人よりも遅く入社したので、この中で一番客観的に会社を見ることができると思いますが、本当に仲の良い会社だと思います。私が入社して一番驚いたのが、展示会の準備をしている時です。特定の人やプレス担当に任せきりにしてしまう企業が多いと思うのですが、弊社は全員で展示会を作っていますね。
清水真紀氏(以下、清水):私は2人よりも遅く入社したので、この中で一番客観的に会社を見ることができると思いますが、本当に仲の良い会社だと思います。私が入社して一番驚いたのが、展示会の準備をしている時です。特定の人やプレス担当に任せきりにしてしまう企業が多いと思うのですが、弊社は全員で展示会を作っていますね。
ブランド数も増えて展示会運営のノウハウは貯まってきたので、準備や運営はシステマティックに進めていますが、関わっている人間が本当に多いので、展示会の準備をしている時は、民族大移動か?という感じで大勢で動き回っています(笑)。でも、そこの連帯感はすごいと思いました。
―なぜそのような企業文化になったと思われますか。
清水:最初は経験もノウハウもまったくなかったので、助け合わなければ本当に成り立たなかった、というのが出発点だと思います。その流れのまま成長してきているので、今もブランド間の垣根がまったくなく、ブランドを横断して助け合いの精神が生まれているのだと思います。
塩澤:私も途中入社ですが、各事業部のトップ同士の仲が良いと感じました。それが事業部のメンバーや現場に浸透しているのが強いところですね。
清水:社内の挨拶ひとつ取っても、とてもちゃんとしていて、気分が良くなりますよね。
鈴木:社長の近藤も、「ファミリー」という言葉をしょっちゅう口にしています。家族なんだから困っている人がいれば助け合うのが当たり前でしょっていう感じなのだと思います。
塩澤:スタッフの人事移動もスムーズにやっています。例えばウサギオンラインで人が足りなければ、別の事業部が積極的にサポートしてくれます。ブランドや事業部をスムーズに横断できるのは、他社では考えられないのかもしれません。
清水:それに、“業務の抱え込み”がないですよね。社内では、それがいけないことだという認識が浸透しています。ですから、色々な部署がしっかりと連携していますよね。
鈴木:新ブランドを立ち上げる時も、色々なブランドの人が垣根を越えて手伝って、絶対に全員で成功させようという気持ちですからね。

2015春夏デビューの「emmi」。スニーカーと合わせるモードウエア「emmi atelier」(写真)と、スタジオスポーツウエア「emmi studio」で構成。
塩澤:複数ブランドを持っている企業だと、No.1とNo.2のブランドがライバル関係にあったりして、冷戦状態になることってよくある気がします(笑)。ですが、弊社の双璧である「スナイデル」と「ジェラートピケ」も仲が良いですよ。
清水:会社はブランド同士を争わせることが多いですが、弊社はそれがまったくないので、妙な意地やストレスはまったくないですね。私は立場上、全ブランドと関わっていきますが、ややこしい人間関係も気遣いも必要ないので助かっています(笑)。
―No.1とNo.2のブランド間が冷戦という話はよく聞きますね(笑)。そうなると評価制度について知りたくなってくるのですが、どのようなポイントで評価していくのでしょうか。
鈴木:明確な評価制度というものはありませんが、社内で評価される人間は、自分以外の仕事まで視点を広げているタイプばかりですね。そういうタイプの人間は、周囲から評価されているので、妬まれるようなこともないですからね。
塩澤:自分のミッションが完璧でも、周りを巻き込めなかったり、困っている人を手伝えないタイプは弊社では評価されづらいかもしれないですね。
―では横のつながりではなく、組織における上下の関係性はどうなのでしょうか。
塩澤:ホールディングス制度にしたのは、“血の通い合った世界一小さい会社を作る”というのが狙いです。組織をコンパクト化して、アルバイト社員の悩んでいることが各事業のトップまで届くような血の通った組織を作りたいという思いで実施しました。
鈴木:まさに「ファミリー」ですよね。近藤はよく社内を回っていますし、店舗にも足を運びます。自分の目で見て、課題やヒントを見つけてくるので、近藤の言っていることは腹落ちします。会議でも売り上げについての話は10分ぐらいで、残りは各事業部の悩んでいる問題を一緒に考えて解決することが多いです。
もし私たちが売り上げ至上主義で、にんじんをぶら下げた成果主義のようなことをやっていたら、428億円(2014年8月期のマッシュホールディングスのグループ全体の売り上げ高見込額)まで行かなかったと思っています。とにかく真摯に自分たちが正しいと思ったことをやり続けたら、結果が後からついてきたという感じです。
―さすが「学生からの注目度ナンバーワン企業※」ですね。このような働きやすい環境が御社の原動力になっているのですね。余計なストレスのないクリアな状態こそ、能力は発揮されますからね。

マッシュグループ2016年度新卒採用サイト(http://www.mash-holdings.com/recruit/)
※繊研新聞社が、15年春卒業予定の全国ファッション専門学校生約1600人を対象に実施した「就職意識調査」で、「注目している企業」の1位にマッシュスタイルラボが浮上した。
■モノ・ブランド・ヒトに手を抜かない 海外店舗でも貫く
―海外展開も好調だと聞いていますが、丁寧なチームビルドや着実なブランドは海外でも通用しているということでしょうか。
清水:今は中国・香港・台湾で海外展開しています。展開ブランドは「スナイデル」「ジェラートピケ」「フレイアイディー」「リリーブラウン」「ミラオーウェン」「ジェラートピケカフェ」の6業態です。店舗数は80店舗を超えております。売り上げも堅調に伸びていて、今期で100億円に到達しそうです。
鈴木:海外展開するときに、モノ、ブランド、ヒトの全てを絶対に手を抜かないということを決めました。例えば海外だと、店舗の内装費が国内の半分ほどしかかからないこともあります。そこで初期投資を抑える企業も多いようですが、弊社は逆の発想で、国内と同じ費用で2倍のクオリティを目指します。ですから、海外の店舗は大理石などの高級素材も多くて高級感を醸し出していますよ(笑)。
海外からのお客様が日本で私たちのショップに来店された後、自国に帰って私たちのショップを訪れたらイケてなかった、というのはブランドとして駄目だと思うんですよね。
販売スタッフの教育も同様で、国内スタッフとまったく同じ研修システムでやっています。接客レベルにおいて国民性の違いを嘆く企業もいますが、結局のところ、笑顔の接客をされるのが嫌な方はどこにもいないですよね。人間ですから、根本の部分は一緒なんですよ。そこをしっかり伝えれば、国内と同じ接客レベルを実現することはできます。
海外展開について近藤は、「洋服を通じて会話したい」ということをよく口にしていますよ。
―出ましたね、近藤語録(笑)。近藤社長は、コンセプトづくりやキャッチフレーズが得意なんですね。
清水:はい。得意ですし、大好きです。すべてのブランドに明確なコンセプトをつけていますが、まず最初にコンセプトを生み出さないと始まらないと思っていますね。ですから、展示会で発表するコンセプトの説明などは、言い回しなどの細かい部分までしっかりチェックしていますね。
塩澤:特に近藤は分かりやすい言葉で伝えることが上手ですよね。こねくり回して複雑にすることはしないです。
―先ほどインバウンドの話がありましたが、実際の状況はどうですか。
鈴木:年々増加していて、本当に驚いています。一番売れている店舗は、全体売り上げの約10%がインバウンドによるものです。
―10%というのはすごい数字ですね。海外のお客様の対応など店舗スタッフさんの業務の幅が広がってきますね。店舗運営において、ウェブやテクノジーを利用した施策などはお考えですか。
鈴木:在庫確認や入庫連絡などの業務などはシステム化できると考えています。在庫確認の時にバックヤードに戻っている間はお客様を待たせてしまうことになりますが、それが3分でも、待っているお客様は2倍にも3倍にも長く感じさせてしまいます。そこを解消するだけで顧客満足度は高まるはずです。
入庫連絡については、多い店舗だと1日30~40件とかあります。それに加えて雑誌やテレビ番組で掲載された商品の問い合わせもあるので、対面接客の時間が確保しづらいという課題があります。
■店頭とオンラインはよりシームレスに
―これからウェアラブル端末やIoTなどのテクノロジーが進化して、バーチャル空間からリアル空間に登場する機会が増えてくると思います。少し先の2018年、3年後の世界を見すえた時、どのような形でそれらを活用していくと思いますか?
鈴木:そうですね。もっとお客様のことを知りたいですね。お客様の欲しいものや興味をもっと知ることで、接客のやり方も変わってきますし、それを商品や店づくり、ブランド構築に役立てることができますよね。そうすることで、私たちのブランドがさらに洗練されて、さらにお客様を満足させることができるようになるはずだと考えています。
老舗ホテルのようなワンランク上の接客が誰でもできるような環境になるといいですよね。
塩澤:そういった顧客体験を、店頭だけではなくオンラインでも提供していきたいですね。早くオムニチャネルの状態が当たり前になり、オムニチャネルという言葉をわざわざ口にすることがなくなる状態を目指していきたいですね。
鈴木:店頭とオンラインストアのシームレスな連携により、私たちのお客様が、商品を欲しい時にいつでもどこでも受け取れるようにするための環境を提供できたら最高ですね。ややこしいことはせず、とにかくシンプルにお客様に喜んでもらえることを考えていきたいですね。
(写真左から)
◆鈴木 努:株式会社マッシュスタイルラボ 執行役員 営業1部部長 店舗運営責任者 兼 株式会社マッシュビューティーラボ 営業本部長
大手ファッション企業で店長・VMD・メンズブランド責任者・支店長を経験。販売代行の会社を立ち上げ、近藤社長と出会い、意気投合し、2009年にマッシュスタイルラボに入社。全国の店舗運営と販売スタッフの教育を担当。
◆清水 真紀:株式会社マッシュホールディングス 広報室 室長 兼 PRコミュニケーションディレクター
美大卒業後、国内大手電機メーカーにて内装設計デザインに携わった後、国内・国外のブランドPRを経て、2014年マッシュホールディングスに入社。
◆塩澤 亮―:株式会社ウサギオンライン代表取締役社長
阪急阪神百貨店で婦人服バイヤーを歴任。2013年、ウサギオンライン設立時に入社。
(前半に戻る)
※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク